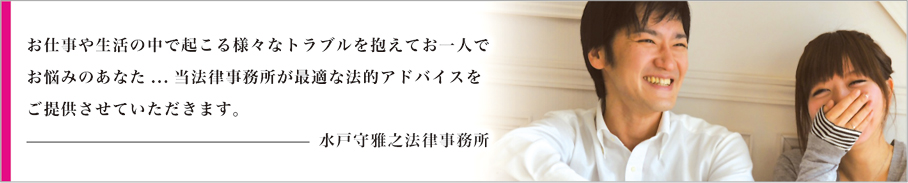 |
||||||||||||||||
 ■遺言
人が亡くなると「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続が始まることは皆さんご存知だと思います。しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるようなさまざまな問題をはらんでいることも多いのです。まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、 違う名前で保管されていたりすると、どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。
■遺産
上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。 そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり(「特別受益者」と言います。)、 故人の看病や世話をした人(「寄与人」と言います。)がいると、 互いの調整が難しくなることが多くあります。他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。
ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるのです。 遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。
■裁判
「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は1年程度を要することもあります。 しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。 また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、「相続の放棄」を考えなければならない場合もあります。例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。 このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。諦めないでください。 法律家がきちんと対応します。 無料相談メール・お電話にて是非一度早急にご相談ください。 [Q] 配偶者が亡くなってこれから相続手続きをしようと思っているのですが、亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。今後どのように手続きを進めていけばよいですか? [A] まず、相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事実および相続財産の内訳を通知する必要があります。もし、まったく付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変ですから、我々のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかと思います。 なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、専門家を中に入れて文書で通知を出してもらったり、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要があるかと思います。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。 [Q] 主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか? [A]まず、生命保険金ですが、これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。もし、保険金の受取人が指定されていれば、その指定された人が生命保険金を受け取ることができ、遺産分割の必要がなくなります。つまり、この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利になるということです。次に、受取人が特に指定されていない場合もしくは法定相続人となっていた場合ですが、この場合はその保険金自体、相続財産となりますので、遺産分割の必要があります。つまり、相続人で話し合った上、お金を分割しなければいけません。 保険契約時の契約書や保険証書などで、受取人を調べ、もし受取人がわからなければ、保険会社にその旨問い合わせるしかありません。ご質問のケースでは、保険をご主人様が自分にかけていたといっても、生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いですので、そのあたりも契約書などで確認してみてください。 [Q] 相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続が開始されたことを知った時)から起算して、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければいけないようですが、被相続人死亡後3年が経過してから、多くの負債がでてきました。こんなときはもう相続放棄ができないのですか? [A] 法律の条文には、「相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければ、以後、放棄ができない(単純承認したものとみなす)」と解釈できる文言があります。 裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。「相続が開始したこと、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月」このことから、もしあなたが最近になって被相続人の債務(借金)の内訳を請求書などから把握したとすれば、その債務を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。また、借金を把握する前に財産をすでに相続してしまった方は、単純承認になりますので、相続放棄自体難しくなります。 |
||||||||||||||||
Copyright 2012 Masayuki Mitomori Law Office All Rights Reserved. |